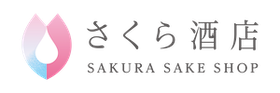- ホーム
- 第三回 東北食べる通信さんコラボページ
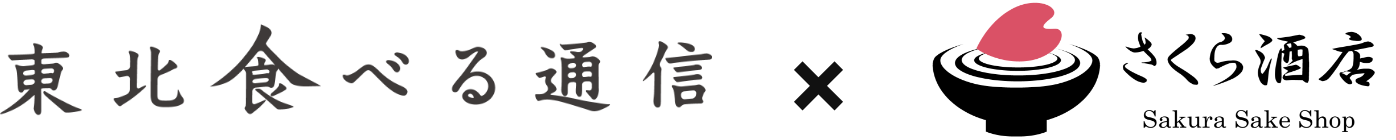
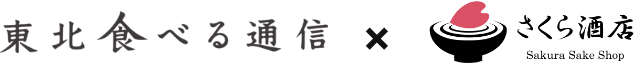
今月の食材に合う、
東北のお酒が飲みたい!
森山知也さんが育てた根菜に合う日本酒はこちら


【今月の日本酒】陸奥八仙

蔵の歴史
元文5年(1740年)、初代・駒井庄三郎氏が近江の国を出て、陸奥の地で酒造りの修行に入ったのが始まりです。糀屋としての創業は1775年。その後、酒造業に参入し、八戸市にて駒井酒造店の名で代々酒造りを続けてきました。 創業銘柄は「陸奥男山」。明治43年(1910年)には他の男山ブランドに先駆けて商標登録し、「男山」の付く銘柄では全国で最初の商標となりました。

昭和に入ると、企業整備令により管内16の蔵と企業合同し、八戸酒類(株)という共同組織で酒造りをするようになります。この体制で50年以上操業するも、世の中は大量生産の時代から品質重視の時代へ。駒井酒造店はより理想的な酒造りを目指し、1997年に八戸酒類(株)から離脱し、独立します。しかし、駒井酒造店の施設は八戸酒類(株)が使っていたため、自分たちは使用を認めてもらえず、自身の蔵から追い出される形で近所の休業する蔵を間借りし、酒造りを再開することになりました。
こうして、新たなスタートを切った駒井酒造店は八戸酒造(株)に社名を変更、新銘柄「陸奥八仙」を立ち上げます。そして2009年には、裁判で自身の蔵を取り戻す判決を勝ち取りました。

現蔵元は9代目にあたる長男の駒井秀介(ひでゆき)さん。杜氏である弟の伸介(のぶゆき)さんとの二人三脚で、更なるステージに駆け上がろうとしています。
アメリカの全米日本酒歓評会、イギリスのInternational Wine Challenge、フランスのKura Masterなど、世界の名だたるコンテストでの受賞歴を誇る一方、若き蔵人たちにはチームでオリジナルの酒を造る企画を設けるなど、常に新しいことに挑戦し続けています。


陸奥八仙のこだわり
使用するお米はすべて青森県産。仕込み水は八戸・蟹沢地区の名水を使用。青森県の地酒として、県産の米と水にとことんこだわり、すっきり爽やかなものから、コクのあるもの、フルーティーなものまで、様々な味わいのお酒を生み出しています。
近年は自然の田んぼの再生を目指し、「がんじゃ自然酒倶楽部」を設立。会員とともに米栽培を手掛けるなど、時代が求める環境と健康に配慮した安全で美味しい酒造りを目指しています。

銘柄「陸奥八仙」の由来 中国の故事・「酔八仙」(八人のお酒の仙人の物語)では、酒仙たちの様々な逸話や興味深い酒の楽しみ方が語られています。飲み手に酒仙の境地で酒を楽しんで頂きたいとの想いを込めて『陸奥八仙』と名付けました。

【ペアリングのミソ】滋味あふれる根菜に、しっかり味の陸奥八仙が合う!
森山知也さんが育てた根菜に合う日本酒はこちら
【コラム】さくら酒店の生い立ち

(前回の続き)
ようやく開業というスタートラインに立ったものの、なかなか思うようにはいきませんでした。販路開拓、資金のやりくり、同業者からの横槍もありました。
無店舗型というと聞こえはいいですが、当時はオンラインショップがあったわけでもなく、やっていたのは飲食店さんへの訪問販売でした。特に営業経験のない僕(駒澤)は、営業の仕方もわかりません。グルメレビューサイトで日本酒にこだわりを持つお店を調べては、飛び込み営業を行う日々。門前払いは慣れたもの。少しでも脈がありそうなお店には何度でも足を運びました。
最初に売れた1本は忘れられないですね。六本木のお鮨屋さんでしたが、何度もしつこく通い詰めた僕に折れたのか、「じゃ、1本もらおうか」と言ってくれたんです。嬉しかった半面、「お酒ってこんなに売るのが大変なんだ」と実感しました。
そんな泥臭い営業活動を繰り返しながら、地道に飲食店さんとの関係性を築いていき、取引先も増えていきました。
しかし、その程度では会社の業績は改善しません。資金も底をつきそうな頃、同時に進めていた輸出へのアプローチがようやく実を結びます。(次回に続く)